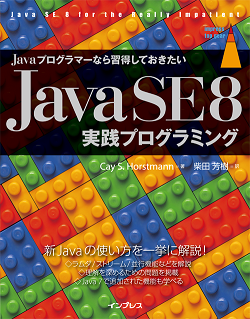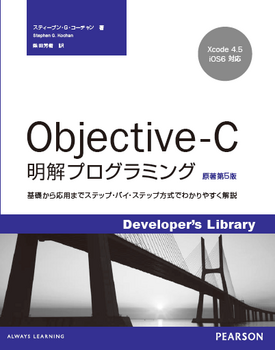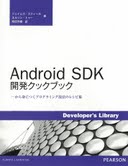第2期Go言語研修が終了しました [プログラミング言語Go研修]
2016年7月に開講した第2期Go言語研修が終了しました。

修了生と私
第2期は5名が修了しました(1名が最終回を欠席)。第1期も入れると合計で14名が修了したことになります。
研修では、『プログラミング言語Go』を事前に読んで、質問をまとめてもらうと同時に練習問題を解いてもらいます。この予習は基本的に私的時間※に行ってもらいます。月に1日だけの業務中の研修では、質問への回答やディスカッション、および練習問題の解答の確認を行います。
※ 予習がすべて私的時間なので、研修の受講は「希望者」だけです。
4月からは第3期を開講予定です。第3期からは過去の実績を踏まえて、6回(半年)で終わる研修コースに変更します。


修了生と私
第2期は5名が修了しました(1名が最終回を欠席)。第1期も入れると合計で14名が修了したことになります。
研修では、『プログラミング言語Go』を事前に読んで、質問をまとめてもらうと同時に練習問題を解いてもらいます。この予習は基本的に私的時間※に行ってもらいます。月に1日だけの業務中の研修では、質問への回答やディスカッション、および練習問題の解答の確認を行います。
※ 予習がすべて私的時間なので、研修の受講は「希望者」だけです。
4月からは第3期を開講予定です。第3期からは過去の実績を踏まえて、6回(半年)で終わる研修コースに変更します。

プログラミング言語Go (ADDISON-WESLEY PROFESSIONAL COMPUTING SERIES)
- 作者: Alan A.A. Donovan
- 出版社/メーカー: 丸善出版
- 発売日: 2016/06/20
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
書籍『変革の軌跡』 [本]

変革の軌跡 【世界で戦える会社に変わる"アジャイル・DevOps"導入の原則】
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2017/01/25
- メディア: Kindle版
2014年9月に『A Practical Approach to Large-Scale Agile Development』を紹介した記事を書いています。
- 書籍『A Practical Approach to Large-Scale Agile Development』
- 書籍『A Practical Approach to Large-Scale Agile Development』(2)
2012年に出版された『A Practical Approach to Large-Scale Agile Development』は、どちらかと言うと技術的側面から書かれています。まだ全部は読み終えていませんが、同じ著者による『変革の軌跡』は組織文化の側面から書かれています。
この二冊で書かれているのと同じような開発をしたことがないソフトウェア担当の「経営幹部」には、残念ながらどちらの本も理解されないのではないかと思います。『変革の軌跡』では、DevOpsにおけるソフトウェア担当の「経営幹部」の重要な役割が強調して書かれています。しかし、この二冊に書かれているような1,000万行を超えるレガシーコードを抱えている企業で『変革の軌跡』に書かれているような役割を果たすソフトウェア担当の経営幹部は、日本にはいないのではないかと思います。
書籍『プログラミング作法』再出版されました [本]
アスキーから出版されていて絶版になった書籍『プログラミング作法』が再出版されました(Kindle版もあります)。著者は、Go言語の生みの親の一人であるRob Pike、そして、『プログラミング言語Go』の共著者であるBrian Kernighanです。
この本に関しては、2011年4月27日に次のように書いています。
1999年に勉強会で使ってから18年が経過したことになります。勉強会で使った勉強会ノートの表紙には、次のように書いています。The Practice of Programming (Addison-Wesley Professional Computing Series)
- 作者: Brian W. Kernighan/Rob Pike
- 出版社/メーカー: Addison-Wesley Professional
- 発売日: 1999/02/04
- メディア: ペーパーバック
1999年に若手技術者に基本的なことを学んでもらうために、当時はこの英語版を利用して第1章「Style」と第2章「Algorithms and Data Structures」の早朝勉強会を海老名プライムタワー(海老名市)、KSP(川崎市)、岩槻(さいたま市)の3拠点で私が出向いて開催しました。その時に作成したのが「勉強会ノート」です。
勉強会ノート: http://www001.upp.so-net.ne.jp/yshibata/TPOP.pdf
その後、日本語版が出版されました。
日本語版を使用して始めた社内教育が「プログラミング作法」教育です。当初は、以下の3部から構成される1日の教育コースでした。
4社※1でソフトウェア系技術者の新卒新人向け教育として行っていましたので、受講生の多くがすでに30代前後です。書籍『プログラミング作法』には多くの有益なことが書かれていますので、この教育では受講生に書籍が配布されていました。
- 「ソフトウェアエンジニアの心得」
- コードレビューの重要性とコードレビュー・ガイドの説明
- 『プログラミング作法』の第1章「スタイル」の教育
「ソフトウェアエンジニアの心得」は、私が雑誌の記事に書いたものが付け加えられる形で内容が年々膨らんでいき、現在の「ソフトウェアエンジニアの心得」教育や講演の内容となっています。
転職後※2は、一日コースではなく、「ソフトウェアエンジニアの心得」と「プログラミング作法(スタイル)」に分離して、別々の社内教育コースとして行っています。「ソフトウェアエンジニアの心得」は、技術系新人の集合教育にお願いして入れてもらい話をしています。今年は子会社※3の集合教育にも入れてもらい、話をました。
書籍『プログラミング作法』の第1章「スタイル」は、私でなくてもできる教育なので、本当は若手エンジニアか中堅のエンジニアが行ってもらいたい内容ですが、残念ながら社内教育としてはまだ私が行っています。※4
※1 富士ゼロックス、富士ゼロックス情報システム、富士フィルム、富士フィルムソフトウェア
※2 リコー
※3 リコーITソリューションズ
※4 富士ゼロックスでは若手技術者が講師となって行ってくれているようです
1 章と 2 章だけでなく、すべての章で有益なことが書かれていますので、是非全体を読んでください。初心者には分かり難い部分も多いですが、その場合には、職場の経験ある先輩に聞いてください。でも、正しく説明出来る人は多くないと思います。「The Practice of Programming」に書かれている内容がすべて説明できるようになれば、一人前のソフトウェア・エンジニアと言っても過言ではないでしょう。ほとんどC言語で書かれていますが、若い人達には是非読んで学んでもらいたい内容です。2000 年 5 月 14 日 柴田 芳樹
拙著『ソフトウェア開発の名著を読む【第二版】』でも紹介しています。